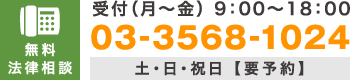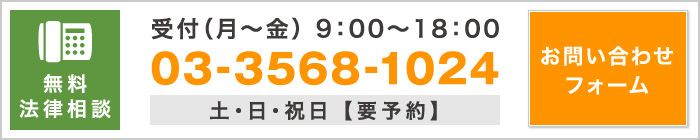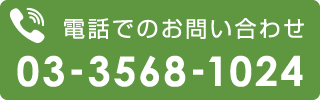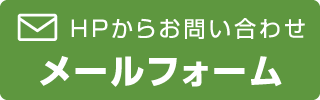東京遺言相続相談センターの今西です
遺言書を作成することによって実現できることの一つとして「相続人以外に財産をのこす」
というものがおります。
遺言書がなかった場合、財産は法定相続人によって相続されることになります。
自分が大切に想っている人が法定相続人でない場合、遺言書が無ければその人に
財産を残すことはできません。
しかしながら、法定相続人以外に、自分の財産を取得させていということもあるでしょう。
例えば
・内縁の妻(夫)
・配偶者の連れ子(養子縁組した場合は法定相続人になります)
・子の配偶者
・先順位の相続人がいる場合の後順位の相続人(子がいる場合の父母や子が存命中の孫など)
・世話をしてくれた知人等
などです。
そのような場合には、遺言書を作成することによって自分の財産を取得させる(遺贈)ことが可能
となります。
この際、気を付ける点として「遺留分」があります。遺留分とは簡単に言うと、配偶者など
一定の範囲にある相続人には、遺言によっても奪うことのできない相続財産に対する割合部分がある
というものです。この遺留分が侵害されている場合は、相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性が
ありますので注意が必要です。
また、法定相続人以外が遺贈を受ける場合、相続税の2割加算など税金面にも配慮が必要です。
遺贈を受ける人を受遺者といいますが、受遺者は遺贈を承認するか、放棄するかを自由に選択できます。
自身が想い、願いを込めて作成した遺言によって法定相続人以外の人に財産を残した(遺贈した)としても、 それを受け取る側(受遺者)に納税資金が無い場合などは遺贈を放棄するという選択をせざるを得なくなるという事態も考えられますので、できることならこの様な遺言を検討される際は法務的、税務的な観点から 実現可能なものを作成して頂くことが望ましいと考えます。